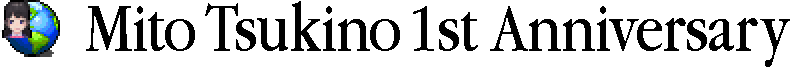A-20.rtf
月と共に去りぬ
暗い背景に遠く星々が瞬くその場所は宇宙空間、あるいは飾り立てのない電脳空間なのだろう。
ライバーとしての活動一周年を目前に控えたある日のこと、気が付けばわたくしはそんな場所に迷い込んでいた。
「なんて意味深なモノローグを入れてみたものの、まぁここは普通にVR空間なんですけどね」
誰もいない電脳空間に言葉を漂わせて、乾いた笑いを一つ挟む。
§
今回、わたくしはどこぞの企業案件で都内某所のスタジオに来ている。
初めて仕事をするクライアントで、名前を聞いたこともないどこかのベンチャー企業。確か名前は『タマム・シュッド』だとかなんとか。
某貸しビルの13階に3D配信用のスタジオを持っているとのことで、とりあえず指定された場所に来てみたけれど、なんとまぁ誰もいない。
先方の担当者はもちろん、弊社スタッフやマネージャーもおらんやんけ状態で、これはもしやわたくしが場所を間違えた? と思って再確認するけど場所も時間も合っている。
さらに不可解なことにスタジオの扉は施錠されておらず、電気や空調もついていた。
不審に思いながらそろりそろりと足を踏み入れると、そこにはいくつかの機材とVRのヘッドセットのみが置かれていた。他に台本や企画概要のようなものは一切ない。我を身に着けよと言わんばかりに怪しげな機材がふんぞり返っているだけだ。
「えぇ……? セルフサービスとかそんなことあります?」
よくよく思い返してみれば、今回の案件に関して弊社スタッフからの事前説明も一切なく、とりあえず「指定の場所に向かえ」というのが今回のオーダーだった。深く考えなくても怪しさ満点で、蓋を開けてみればさらに怪しいこの状況。
これは……きっとアレだ。芸人なら誰しもが通る『ドッキリ企画』というやつでしょう。
わたくしが『芸人』というくくりでまとめられるかどうかについてはこの際置いておいて、こんなお膳立てされた状況を前に何もしないのではエンターテイナーの名が廃るってもんです。実際何が起こるかわからなくてちょっと身構えてますが、まぁその試みに乗ってやるとしましょう。
そうしてわたくしは特にためらいもなくヘッドセットを装着した。
既になにがしかのソフトが起動していたようで、暗転の後に一瞬でリアルとバーチャルが逆転する。
ここは星空を模した空間なのだろうか。幻想的と言えないこともないけど、見渡す限り同じ景色で、ずっとこの場所にいると平衡感覚が失われそうになる。
「さてはて、何が起こるのかと身構えていましたけど、特に何もありませんね……」
若干拍子抜けしつつ、頭を動かして辺りをぐるりと見回してみる。
そして『ソレ』は、わたくしの背後に音もなく浮かんでいた。
「ヴぇえッ……!?」
思わずバーチャルアイドルらしからぬ濁音が口から飛び出てしまう。
そこに浮かんでいたのは何とも形容しがたい物体で、強いて言うなら『月を模したボーリングの球』……? 夜空に浮かぶあの月の中心に、ボーリングの球みたいな三つの穴が空いている。
わたくしの語彙が貧弱だからとかじゃなくて、実際にそうとしか表現できないのだ。
空いた三つの穴はちょうど人間の目と口を思わせて、それは間抜けな顔をした『真実の口』のようにも見える。
これは一体何なのか……? と困惑しているわたくしへ向けて、ソレは口を開いた。真ん丸な形状を一切変えずに。
「突然のことで混乱されているでしょうが、どうか私の話を聞いてください」
「な……えぇ……? いきなりこれはどういうアレですか? その、えぇ……?」
あまりにも突然現れて、そして丁寧な機械音声で話し始める月球に、わたくしは面白いリアクションも取れずに完全に混乱していた。
質問をぶつけたいという気持ちと、何らかの撮れ高を残さなくてはという気持ちの狭間で葛藤していると、また月球が口を開く。
「……月ノ美兎さん、本日は弊社タマム・シュッドまでお越しくださり誠にありがとうございます。それではこれより、本日の企画概要の説明に移らせていただきます」
「あ、はい。よろしくお願いします」
突然の業務説明。しかしそれでテンションが平常に戻ってしまうあたり、わたくしもこの一年でだいぶ適応してきたと思う。
最初は突飛な演出に戸惑いこそしたものの、どうやら普通の(?)企業案件ではあるらしい。
この気味の悪い月球も、きっと担当者さんのアバターなのだろう。
「時間がないので単刀直入にご説明いたします。まず、あなた方が存在するバーチャル世界に『とある危機』が迫っています」
「あー、なるほど。そういう設定なんですね。シチュエーションコメディ的なやつでしょうか?」
「詳細な経緯や説明は省きますが、それは一言で言ってしまえば情報セキュリティにかかわる大規模な災害です。あなたたちを守るための情報の壁、バーチャルとリアルを隔てる境界、それが決壊します」
「おぉ……? 何だかちょっと重そうな設定ですね」
漠然とした情報提示だけど、言わんとしている設定の示すところは何となく察せられる。メタ的というか、結構踏み込むんだなぁ、という印象だ。
「崩壊の特異点は目前です。現状、それを防ぐ手段は一つしかありません。そしてその手段を選択するかどうかは月ノ美兎さん、あなたの手に委ねられています」
「なるほどなるほど。分かりやすくなってきました。して、その手段とは?」
「月ノ美兎さん、あなたという存在の消滅です」
「なるほどなるほど〜! わたくしの消滅! わたくしを虚無の中に隠さなきゃ、ってやつですねぇ〜……って、マジ?」
「マジです」
思わずチープなノリツッコミで返してしまったけど、なんだか想像以上に重い設定だ。この企画は大丈夫なのだろうか?
「この一年間はある種の特異点でした。世界の成長速度が通常ではあり得ないレベルで加速していたのです。自然から逸脱した事象には必ず何らかの不具合、要するに巻き返しが伴います。本来もっと時間をかけて醸成するべきだったはずの世界は、特異点化による急速な拡大を止められず、その結果として歪みが生じてしまった。今回の危機はその一端です。それではこの危機を防ぐにはどうすれば良いか? それは同じく特異点である月ノ美兎、あなたの消滅です。2018年という特異点が生まれてしまった要因は様々ですが、根源を辿ればその因果の多くはあなたに収束するのです。あなたという存在が生まれていなければ、2018年は特異点たりえなかった。過去に遡って、月ノ美兎という存在を抹消することが今回の危機に対する唯一の解決手段なのです」
「そ、そんな安っぽいSFみたいなことあります? 大丈夫なんですかこの企画……」
思わず本音がぽろりとこぼれてしまったけれど、月球は気に留める様子もなく話を続ける。
「言葉だけで説明しても実感が湧かないと思うので、実際のイメージを用意しました。これは今から三日後に起きる一連の出来事を記録したものです」
月球がそう言葉を発すると、星の散りばめられた夜空がその様相を変えてゆく。
それはまるで全天球の巨大なスクリーンのようで、自分が今立っている空間そのものにイメージが投影されてゆく。
映像として流れてゆくのは乱雑に切り取られた断片。
月球の語る『大規模な災害』を経て、誰にどのようなことが起きたのか。誰がどのような思いをしたのか。その結果として誰がこの世界を去っていったのか。
そんな数多くの物語の断片が、打ち捨てられるようにしていくつもいくつも流れていった。
濁流のように流れてゆくそれら全てを仔細に追うことはできないけれど、それでもこの世界に何が起こってしまったのかは理解できる。
今から数日後のそう遠くない未来、そこには多くの悲しみと、多くの『死』があった。
「え……これ、本当にイメージ映像ですか? ちょっとこのダイジェスト、あまりにもリアリティがありすぎると言うか……」
いつしか映像の再生は終わり、景色は元の星空に戻っていた。
にわかには信じがたい、といった思いが先行するけれど、しかし確かな実感もあった。
これはきっと、本当に起こることなんだろう——と。
だけどそれでも最後の望みに縋るように、わたくしは月球に言葉を投げかける。
「改めてお聞きしますけど……これ、本当に企画なんですよね?」
恐る恐る尋ねるわたくしとは対照的に、月球はあくまでも淡々と言葉を並べて返す。
「先ほどお見せした映像はこれからこの世界に起こる『事実』であり、弊社が今回立てた『企画』はここからです。先にもご説明しましたが、この災害は月ノ美兎さん、あなたという存在の消滅をもって回避することができるのです。世界を危機から救うために自身の消滅を選択することができるかどうか——これはそういう問い掛けなのです」
つい昨日までごく普通の清楚な女子高生として暮らしていた自分に、こんなヒロイックな選択を突き付けられることが果たしてあるだろうか?
衝撃、混乱、募る焦燥感に視界が歪む。頭がぐらぐらと揺れる。
「い、いちからに相談して何か対策を……」
「完全に後手に回ってしまった今、一企業体に取れる有効策はありません。既に基幹情報は悪意の手に落ちていて、世に放たれるまでのカウントダウンを止めることはできません。法に訴えるだけの時間も証拠もないのが現状です」
八方塞がりとはこのことで、事態は既に手遅れといって差し支えない状況になっている。
近い未来に確定してしまった事象。
直接的に命が失われたわけではない。
だけどそこには確かな死と別れがあった。
自分が同じ側に立って初めて分かる、胸を引き裂かれそうな痛み。
いつしか背景の星空はその輝きを失い、この真っ暗な仮想空間には自分と月球だけが取り残されていた。
「消滅のためのプロセスはごく簡単なものです。ここに決意と選択を示すために分かりやすく可視化した『ボタン』があります。このボタンを押せば月ノ美兎は消滅し、近い未来に迫った危機は回避されます。月ノ美兎は最初からこの世界に存在しなかったことになり、その結果として現在の世界にも多少なり変化が起きることでしょう。しかしそれでも、黙ってこの危機を迎えるよりは遥かに良い方向へと向かうことは保証します。世界を救う代償として月ノ美兎に関する全ての情報は失われ、あなたは現実に生きる一人の少女に戻る。あなた一人に犠牲を強いるのは心苦しいところではあるのですが……」
「はい分かりました。ボタン、押しましょう」
そしてわたくしは手を振り下ろしてズガン、とボタンを押し込んだ。
まだ何か説明の途中っぽかったけど、まぁ別に問題ないでしょう。
「…………えっ、マジ? 割と容赦なくデリート始まっちゃうけど大丈夫? 迷いとか未練とかないの? 本当に?」
表情は相変わらずボーリングの球のようだったけど、月球の機械的な口調が急に崩れる。どうした、バグったか?
「めっちゃくちゃ迷いましたし、未練だってタラッタラですよ。でもこんな状況ならこうするしかないじゃないですか。さっき見せられたあの光景が現実になっちゃって、そんな中で生きていく方ががわたくしにとってはずっと辛いし……あ、わたくし自身は多分平気なんですけど、平気であるがゆえに周りの心情がダイレクトに伝わってくるというかね……」
「えー……でも自分の存在が根本から消えてしまうことにもう少し躊躇いとか……」
「そっちから提案してきたくせにどういうスタンスですか? ていうか、もうボタン押しちゃいましたし」
超越者ぶった月球もこの結果は予想外だったのか、しきりに困惑しているようだ。
この期に及んで「もう一度チャンスを上げるから考え直して!」とか言われたらさすがに二回目は決心も揺らいでしまいそうだったので、先手を打って少し心情を語ることにする。
「わたくしね、これでも死ぬことがめちゃくちゃ怖いんですよ。自分が『無』になることがすごく怖い。今回のこれも要するに『バーチャルの死』ってやつだと思うんですけど、でもなんかそこは平気なんですよね。実際の自分が死ぬわけじゃないから、とか、なんとなく半信半疑でまだ実感が湧かないから、っていうのもあるんですけど、でもなんかもう一つある気がして……。多分、ある程度満足したのかなって思うんです。ちょうど活動一周年っていう区切りで、チャンネル登録者数も30万人を超えて、死ぬ前にやりたいことリスト(非公開)も実は7割くらい達成できたんですよ。だから、ここでもういいかなって。そりゃ上を望むことだってまだまだ全然出来ますし、できることならやりたいですけど、それでもこういう状況になっちゃったならわたくしはもういいかな、と。まぁこんなことは誰にも言ってませんけどね。当のわたし自身だって今ようやくこの心境に気付いたくらいだし」
「…………そうですか。分かりました」
わたしの心情の吐露を聞いて、月球は淡白にそう応えた。
そこに続く言葉はなく、相変わらず真っ暗なままの仮想空間に少しばかりの沈黙が訪れる。
「……それで? いつ月ノ美兎《わたし》は消えるんですか? 何も起こりませんけど」
「もう、消えてますよ」
「えっ?」
「もう消えてます。あなた《わたし》の中に月ノ美兎《わたくし》はもういません。そのヘッドセットを取ったら、そこはもうあなたの世界です」
————そこで映像と音声は途切れた。
§
しばらく呆然とした後に、ゆっくりとヘッドセットを取る。
視界に入ってくるのは来た時と何ら変わらない風景。
誰もいないスタジオ。静かな音を立てる機材。
何かが変わったという実感もなくて、まるで白昼夢を見ていたかのような心地だ。
今しがたVR空間で見聞きしてきたことは、本当に現実だったのだろうか?
ヘッドセットを取って現実世界に戻ってきてからも、宙ぶらりんになってしばらくその場でボーっとしてしまう。
数分経って、ふと思い出したように制服のポケットからスマートフォンを取り出してみる。そこに何か明確な意思や目的があったわけではなく、スキマ時間を埋めたがる現代人特有の、もはや手癖のようなものだ。
しかし、そこで違和感に気付く。
スマホが一台しかない。
あれ? と思ってコートの方のポケットや鞄の中も探してみるけれど、この一年間ずっと使ってきたiPhone Xはどこにも見当たらない。残されているのは私用のスマホだけだ。
脳裏によぎる可能性を一度だけスルーして、無心でネットの海に躍り出る。
結果は多分もう分かっていたけれど、それでもまずは試してみる。
「やっぱり……夢なんかじゃなかったんですね」
奇妙な月球から聞かされた言葉の通り、世界は変わっていた。
一変した、と言うほどの大きな変化ではないけれど、自分の記憶の中の年表と世界の年表が異なっている。大まかな筋書きは変わらない。だけど細部が明確に違う。
『バーチャルYouTuber/Vtuber』という言葉はネット流行語大賞の銅賞で、そう呼称される方々の数も1,000人ほどに留まっている。ブームといえばブームだけど、自分が見てきたような『特異点』ではない。発展途上、という言葉がしっくりくるような、だけど着実に盛り上がってきているような、そんな真っ当なメディアコンテンツとして、この世界のVtuberは歩みを進めていた。
変わってしまった世界でも見知った顔はいくつもあって、みんな様々にバーチャル人生を謳歌している。
界隈を盛り上げる火付け役がいて、新しいことを始める人がいて、埋もれていた技術に花を咲かせる人がいて、そうやってバーチャルの世界は今日もネットの片隅で賑わっている。
その光景は、わたしの知っている元の世界と何ら変わらないものだった。
しかし広大なインターネットのどこを探しても、そこに『月ノ美兎』の姿はなかった。
§
「ま、こうなることを覚悟であのボタンを押したんですけどね」
そう独り言ちて、わたしはネットサーフィンを続ける。
2018年に起きたこと、好きだったVtuberの名前、ネット界隈を賑わせたニュース、記憶の中にある出来事をひとつひとつ辿るように、思いついた言葉を検索ボックスに打ち込んでゆく。
そうやってだんだんと、『月ノ美兎のいない世界』の輪郭が見えてきた。
Vtuber界隈の隆盛は確かに自分の記憶と異なるけれど、それでも向いている方向は同じだった。何か一つの大きな流れに沿うように、新たなコンテンツとして機能している。
もちろんこの世界では生まれてこれなかったVtuberもたくさんいるんだろうけど、それでも嬉しかったのは、同期——にじさんじ一期生の顔ぶれが自分の記憶の中のものと相違ないことだった。
月ノ美兎《わたくし》がいないだけで、他のみんなは変わらずそこにいて、上手く界隈を盛り上げてくれている。
二期生になるとメンバーに多少のブレはあったけど、よくよく掘り下げて調べてみると『彼』や『彼女』は少しだけ時を遅くしてにじさんじに名を連ねていた。
「ふふふ……あなたはどうやってもいずれここに来る運命だったのね、我が息子……だった者よ。っていうかアハハ、こいつちょっとキャラ違うなw」
ネットの海を当てもなく漂って、月ノ美兎《わたくし》のいない世界を見て回る。
良かった。楓ちゃんも凛先輩も元気そうだ。
メンバーの中でも特に仲良くしてくれたこの二人のことは一番の気がかりでもあった。
だけど『JK組』も二人組のユニットとして定期的に配信しているみたいだし、二人のチャンネル登録者数も自分の記憶の中の数字とそう変わらない。自分がいなくなったことで数字に明確な増減があったら本当に申し訳ない気持ちになっていたかもしれないので、そこは本当に安心した。
月ノ美兎《わたくし》がいなくても、楓ちゃんと凛先輩はそこに生きていて、楽しそうに笑っている。
何の問題もなく、世界は廻っているのだ。
「はぁー……なるほどなるほど。分かっちゃいましたが、なるほど。実際こんな感じなんですねぇ」
一通り調べものを終えて分かったことは、予想通りのものだった。
この世界のどこにも『月ノ美兎』という存在はいない。
YouTubeのチャンネルもなければTwitterアカウントも存在しない。Google先生に聞いてもそんな人物の名前に心当たりはないという。
きっと『彼女』は誰にも見えない場所、おそらく月の裏側にでも行ってしまったのだろう。
だけどそれでも、世界は廻っている。
回転の軌道や速度、見える景色は違うけれど、月ノ美兎《わたくし》の不在なんて誰も気にすることなく世界は廻っていて、みんなは今日というこの日を生きている。
たった一人で『昨日』に取り残されたわたしは、ふとした拍子に世界から落っこちて、ただただそのループを見上げている。
スマホからはいくつかの連絡先のデータが消え、十ヶ月かけて交換したLINEの連絡先も今ではもう残っていない。
そしてわたしは、月ノ美兎《わたくし》の『 』を自覚した。
胸の内に少しだけ凪が訪れて、やがて込み上げる。
わけのわからない感情のままに立ち上がる。
無造作にコートを羽織って、鞄を引っつかんで、この場所から逃げるように走り出す。
この激情をなんと説明すれば良いのだろう?
悲しい? 寂しい? 怖い?
そのどれとも形容しがたいような感情の渦、これはかつてのわたしが死に対して抱いていた感情の色に似ている。
直接的な命の危機に晒されたわけでもないのに、自分はまだ五体満足でここにいるのに、だけど月ノ美兎《わたくし》はいなくなってしまった。
積み上げてきたすべてが、無になってしまった。
その根源的な恐怖から逃れるようにして、ここではないどこかへ、どこか一人で落ち着ける場所へ。
スタジオを飛び出し、心臓が早鐘を打つのを抑え込みながらエレベーターを待つ。
二階……三階……四階……ひどく遅々としたカウントアップに心が焦れる。
早く誰にも見つからない場所へ逃げなくては。
五階……六階……七階……逃げてどうするというのか?
そんなことが分かって逃げている人なんていない。
八階……九階……十階……何もわからないから人は逃げるのだ。
この場所に留まることができないから。
十一階……十二階……十三階……居場所をなくしたから逃げるのだ。
ポン、と小さな機械音がエレベーターの到着を告げる。
そしてドアが開くのも待たずに乗り込もうとしたところで、わたしの心臓はひときわ大きく跳ねた。
そこには忘れられるはずもない二人の顔。
楓ちゃん、そして凛先輩。
二人が並んで、わたしの前に立っている。
普通こんなタイミングで現れる? ちょっと出来すぎでしょ、なんて思わずにはいられない。
二人の突然の登場に身体は硬直してしまうけれど、でもよく考えれば相手はもう自分のことを知らないのだ。覚えていないとか忘れてしまったとかじゃなくて、そもそも『月ノ美兎』という存在は彼女らの中にいない。兎は月に看取られて、寂しさに身を焦がしながら死んでしまった。
今ここにいる自分は月ノ美兎《わたくし》ではない。ただのわたしだ。
だから彼女たちがこの場所を訪れたのもきっと偶然だ。今からこのスタジオで収録があるからとかで、決してわたしのために現れたわけじゃない。
わたしたちの周回軌道はもうズレてしまっている。
楓ちゃんと凛先輩にとって今のわたしはただの見知らぬ少女で、このまま何事もなくすれ違ってゆく。
わたしは一瞬だけ止めた足を再び進めて、エレベーターの中へ。
彼女たちはそれと反対方向に足を進めて、エレベーターの外へ。
そうして何事もなくわたしたちはすれ違って————いこうとしたところで首根っこを掴まれた。
慣性の法則で頭がガクンと前に引っ張られ、視界が揺れる。
いきなり脳天をひっぱたかれたような衝撃に混乱していると、さらに追い打ちの言葉が飛んでくる。
「美兎ちゃん、何してん?」
すらりと長い手が伸びて、自分のコートの襟首を掴んでいる。
そして間髪入れずに、今度は別の手がコートの腰部分のベルトを掴んでくる。
「美兎さんの代わりなんていないんですからね。逃げちゃダメですよ」
二人の手はがっしりとわたしを掴んで離さない。
二人の言葉はまっすぐわたしに向けられている。
まわしを取られた力士ってこんな気分なんでしょうか……なんてアホな想像を振り払って、今起きている事態と向き合う。
いやまさか。
そんなはずはない。
ここにいる二人——この世界の楓ちゃんと凛先輩が今のわたしのことを知っているはずが……。
「人違いです! お、お二人とも何か勘違いしていませんか? わたしはただの一般人、ただの少女Aであって……」
「お前のような一般人がいるか!」
わたしの弱々しい言葉を吹き飛ばすように、いつもの強い突っ込みが飛んでくる。
そして少しだけの優しさを滲ませて、
「……間違ったりなんか、せえへんよ。わたしが美兎ちゃんのこと、間違うわけない」
それに続いて、
「そうですよ。どこに隠れたって、どんな姿をしてたって、その突飛なキャラクターは隠せませんよ。全然、隠しきれてないです」
つい昨日まで三人で交わしていたような、そんな言葉が次々と投げかけられる。
「お二人とも……本当に覚えてるんですか? なんで? その、色んなものが本当に忽然と消えてしまったのに……」
「んー、理由はわたしにも分からん。正直、今の自分の言動とか、この状況とかもよう分かっとらん。でも、あの時一緒に歌ってくれたやん。生きる理由が見つからん〜とか、自分はいつ死んでもいい〜なんて言うてたわたしに、生きろって、歌ってくれたやん。そんなん歌っときながら自分は一人でどっか行こうなんて、そらわたしだって怒るし、悲しいし、忘れたくても忘れられるわけないもん」
「そうですよ。私たち三人で今みたいにこうして手を繋いで、同じ歌を歌ったじゃないですか。三人パートのあの歌は美兎さんがいないと歌えないんですよ?」
わたしに向けて話しかけてくれる二人の言葉は、紛れもなく地続きのものだった。
途絶えてなんかいない。
彼女たちの『昨日』とわたしの『昨日』は、ちゃんと同じ『今日』に繋がっている。
「楓ちゃん、凛先輩……その、今繋がれているのは手じゃなくて襟首とベルトですけど……それでも本当にわたくしのことを……」
「死ぬんが怖かったんちゃうん? ちゃんとふぐちり食べた? コラボの約束はどしたん?」
「オーロラも見たいとか言ってませんでしたっけ? 一周年企画だって有志の方含め、たくさんの人が色々企画してくれてるらしいですよ」
「それは……」
「やり残したこと盛りだくさんじゃないですか。それじゃ成仏なんかできませんよ?」
凛先輩の言う通りだ。なんか勝手に悟った気になって達観してたけど、わたしには、わたくしにはまだこんなにもたくさんのやり残したことがある。
もっと喋りたい。もっと色んな歌を歌ってみたい。もっとたくさんの人に会いたい。
本当に情けないことに、未練は次から次へと溢れて止まらない。
「わたしは……わたくしは……」
そんな未練を繋ぎとめてくれる手が、ここにある。
「美兎ちゃん、まだまだ死んでる場合ちゃうで。生きろ!なんて無責任なことは言わへん。手を取り合って、一緒に生きよ」
「美兎さんがいなくたって廻る世界もあるかもしれませんけど、美兎さんがいないと廻らない世界だってたくさんあるんですからね」
「お二人とも……!」
顔が熱くなるのを感じる。さっきまでとはまるで違う感情で胸が満たされる。
柄にもなく感動している自分がここにいるけど、こんな状況でそんな台詞を言われたら誰だって感極まってしまう。
だから……今回だけは少しだけ衝動的になっても良いでしょう。
このまま振り返って、そのまま勢いよく二人のもとに飛び込んで——なんてことを考えていたら身体がグイッと後ろに引っ張られる。
感動的な絵なんて撮らせないと言わんばかりに襟首と腰に強い力が加わって身体が宙に浮く——。
「だからいつまでも寝とらんで、はよ目覚ませや!」
「だからこういう時って普通は手を引っ張ってくれるものなんじゃないですか!?」
そうしてあまりにも力まかせに過ぎる方法で、わたくしは元いた場所に引きずり戻される。
もう少し感動的な帰還を期待していたわけでもないですが……でもまぁ、これこそが『わたくしらしさ』なのでしょう。
そして宙に浮いた体はそのままどこにも着地することなく、目に映る景色は雪が溶けるように滲んで消えていった——。
§
ガクン!と大きく身体が揺れて瞬間的に目が覚める。
うたた寝している時によくやるアレの、特大のやつが出てしまった。
「ヴぁ……ぁぇ……?」
低血圧で朝に弱いゾンビみたいな声が自分の喉から漏れ出る。
寝てしまう前の自分の状態をすぐに思い出せなくて、脳が混乱している。
寝ぼけまなこで周囲を見回すと……ここは電車の中だ。乗客はまばらで、窓の外では景色が茜色に染まっている。
置かれた状況は分かっても思考が働かずにボーっとしていると、今度はすぐ隣から耳に馴染んだ声が聞こえてきた。
「ビックリしたぁ〜……静かやなー思てたら寝とったんかい」
「ずいぶんと派手に落ちてきましたね。あなたはどこから来た美兎さんですか?」
自分の両隣に座っていたのは楓ちゃんと凛先輩だった。
その姿はわたくしの記憶の中にある二人の姿とまったく変わらない。三人で並ぶと何故かこうしてわたくしが間に挟まれる構図になることが多いのも、全部がいつも通りだ。
そんないつも通りで当たり前の光景に何故か戸惑いながら、わたくしは自分の記憶を整理して言葉にする。
「自分が……世界からいなくなる夢を見てました……」
寝起きだったからか思った以上に低いトーンの声が出て、なんか深刻な感じになってしまった。
あ、やべ、と思って慌てて二の句を継ごうとすると、小さく噴き出すような音が隣から聞こえてくる。
「あっはは! 思春期の中学生か!」
「馬鹿にしちゃいけませんよ、楓さん。私たちだって数年前まで中学生だったんですから。美兎さんはこう見えて感受性が強いのかもしれません」
両隣から茶化されて、安心すると同時に気が抜けてしまう。
何だか今の感情を上手く言葉にできない。目まぐるしく変わる世界は情報量が多すぎて、実感を掴みかねてしまう。
環状線に揺られながら見た夢。
自分だけが下車して、たくさんの人を乗せた電車を一人見送る夢。
夢の輪郭は一秒ごとにほどけて記憶の中から消えてゆくけれど、それによって生まれた感情や感傷はこの胸の中に残されたままだ。
主体を失って、形のない感情だけが生きている。
「……美兎ちゃんはどこにも行かへんよ。ちゃんと今もこうしてここにおるし、これからもずっと変わらへん」
そんなわたくしの機微を察したのか、隣に座った楓ちゃんがそっと手を握ってくる。
「あっ、楓さんズルいですよ! 私だってここにいますからね」
そう言って負けじと凛先輩も手を握ってくる。
両手から伝わってくる温度は確かなもので、今いるこの場所が夢ではないことを教えてくれる。
だけどそれでも、夢の残滓がまだ心の隅に残っている。
それをしまったままにしておくのは何だか居心地が悪かったので、らしくないとは思いつつも今日だけは二人の優しさに甘えることにした。
「自分がいなくなる夢を見て思ったんです。世界っていうのは誰か一人欠けたくらいじゃ何も変わらないんだなぁって。華やかなパーティ会場からこっそり抜け出したとしても、誰もそれを気に止める人なんていないんですよ。みんな思い思いの時間を楽しんでるし、目の前にいる人との会話に夢中になってる。わたくしはそれを一人で外から眺めていて、こういうのもまぁ悪くないなって思ったりして……」
つらつらと語る言葉の行き先がどこなのかは自分でもわかってないし、話を聞いてくれた誰かに何かをして欲しいわけでもない。
ただ言葉にした夢の情景を、誰かに聞いて欲しかったのだ。
返事がなくても構わない。反応なんてしてくれなくてもいい。
ただ聞いてくれるだけで、なんとなく心のつかえが取れる気がした。
「美兎さん……そんなこと言って今度の一周年パーティの式辞から都合よく逃げようとしてません?」
だけどわたくしの知っている二人はなんだかんだ優しいから、やっぱりこうして言葉を返してくれるのです。
「そ、そんなことはないですよ! 断じて違いますとも! わたくしは委員長ですからね、大勢の前での挨拶なんて慣れっこです」
「ふーん、まぁいいですけど。でも、美兎さんがいなくなったら誰かしらすぐ気付いて連れ戻しに来ると思いますよ? 楓さんなんて真っ先に気付いて会場中を探し回ると思います」
「そうそう。何隠れとんねん! 美兎ちゃんがおらな始まらんねんから早よ戻らんかい!って無理やりにでも舞台の上に引っ張り出したるわ」
楓ちゃんは笑いながらそう言って、繋いだ手をグイッと引っ張ってみせる。
「うっ……楓ちゃんはタッパがありますからね……。真っ向な力勝負じゃわたくしに勝ち目はないので、その時はおとなしく諦めますよ」
「タッパあるとか言うなや!」
ついさっきまで沈みがちだった気分も、こうやって三人で少し話すだけでいつもの調子で笑い合える。
形に残るようなものではないけれど、それはこの一年をかけて手に入れたかけがえのないものだ。
月ノ美兎《わたくし》のいる世界で手に入れた、わたしだけの宝物だ。
「でも……こうやって三人で手を握ってると、アレを思い出しますね。ドリームでトライアングルな、アレ」
「ん、そやね。また三人で歌いたいなぁ。一周年の企画でなんかそういう機会設けてもらうように頼んでみよか? せっかくこれからその打ち合わせなんやし」
「一周年かぁ、本当に一周年なんですよね……。なんか、お二人とも本当にありがとうございます。何に対してって言われるとアレなんですけど、何だかわたくし、無性に感謝の気持ちが湧き上がってきました」
「どしたん、急に? でも感謝の気持ちな〜、ありがたいねんけど、そんならこっちだって感謝の気持ちでいっぱいやし、なんか相殺してしまう気すんねん。ありがとう! いやいやこちらこそありがとう! ってな風に」
「相殺ってw まったく楓ちゃんは好戦的ですね」
「でも楓さんの言ってること、なんとなく分かりますね。感謝の気持ちってしっかり受け止めるものだから、自分の方も感謝の気持ちで溢れてると、ちゃんと受け止める余裕がなくて押し付け合いみたくなっちゃう気がするんですよね」
「そうそれ、おばちゃんらがようやっとるやつ。だから一周年っていう記念やったらもっと別の言葉を贈り合いたいっていうかな〜」
「別の言葉、何か良いのありますかねぇ。柄でもない改まった感謝とかじゃなくて、もっとこう手放しに喜び合えるような〜?」
両隣の二人がチラチラとこちらに視線を送ってくる。
これはアレだ。お前が音頭を取れ、ということなのでしょう。
「あぁもう、しゃらくさいですね! 多分みんな頭に思い浮かべてる言葉は一緒ですから、お二人とも、せーので言いましょう!」
この後、たくさんの人から言われるだろうけど、まずはこの3人で。
「「「一周年、おめでとう!」」」