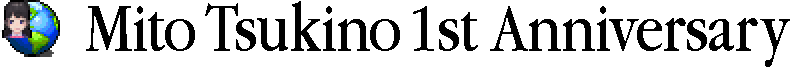Aikawa.rtf
つきのみるひと
砂礫が絡んだらしく、車輪が削れるような音がした。窓から見える光景——表示されている地図によれば、バッカスの海のほとりらしい——がしだいにゆっくり流れていくようになった。速度に目が慣れてきて、たまに咲く花が目に入るようになった。こんな所に向日葵まで咲いていている。向日葵は真っ直ぐ青い星を見ている。車体が前後に揺れて、ひときわ大きな音を立ててついに止まる。車輪の削れる残響が奇異な悔いを惜しみながら消えていった。
手持ち無沙汰で、ほおづえを突いて窓から外を眺める。少し頸を捻って、翳りが出てきた空に目を遣った。残映もおぼろに、大きく見える青い星が、白い靄をまとっている。遙かな上の方、三十八万キロの向こう、佇む大きな天体。背景は黒く、青い穴が空いて、中にいつも靄と緑が渦巻いているように見える。その明るさも、もっと向こうにある天体——恒星である、太陽と呼ぶソレの光が反射しているからで、今窓の外に見えている光景も、遙か向こうから来る光で見えていると考えると——少しぞっとしない話だと思う。
車内は静かで、見渡せば、寝ているか端末をいじっているかで、鳴く泣き虫の子でもあれば静かに歌うこともできたろうに、暇を殺すのにまたぞろ外を見るしかない、と窓に顔を向けると、そこに車掌が写っていた。
「ああ、屍のようなところにようこそ、」
くぐもった、掠れた声は聞き取りづらく、不快と言うより、いぶかしむ気持ちがわき上がった。
「屍、って言いますけど、墓ならまだしも、そんな事実は」
「失敬、唇亡びて歯寒しといいますか、星を離れてしまうと、人生を憂うこともあるでしょうに」
「あ、いや、旅行で、」
「こっちに来るなんて、まったく勇気に勝るところがあるお方ですね」
なにを言おうとしても、金剛像のようにまったく譲らなさそうな、あるいは独り言、のれんに腕押しの問答に、疼きが後頭部を撫でていく。
「……、いつ頃動き始めるんですか?」
「何かお急ぎで?」
「……いや、わたくしはいいんですけど、乗客の方々とか」
静寂が空気の濃淡を奪ってしまっている中で、余韻が、徒情けとか、対価を求めたように、未練を残してく。
「あの、なにか……」
車掌は大げさに首を振って、袖をまくって腕時計をさらけ出した。おもむろに時計を自分の顔に持ってきて、一時間、とだけ呟いた。刹那にまた大きく車体が揺れ、車輪が削れる音が響き始めた。
「車輪が鳴くところがねえ、止まる場所なんですよ」
車種はそれだけ言って、床を甲高く、硬質な足音を鳴らしながら小気味よく去って行った。車体はゆっくりと速度を上げ、車掌の足音のようにリズムよく車体を揺らし始めた。バッカスの海、森のほとりが見えてくると、細風が過ぎ去って、夕霧が拡がった。水滴が窓に点々と張り付いていくと否や、輝きを反射して綺羅星を訴え、駆け抜ける森に最後の白無垢で飾り立てるように、見事に流れていく。
額に掌をあてがって、胸の奥からゆっくりと息を吐いた。ぬるくなった呼気が充満して、散逸していく。温度が宙を歩いていって、掌に体温だけが感じられる。少し息を止めると、張り詰めた空気が、小刻みに揺れているのを感じられる。足裏には定期的な振動があって、意識がもうろうとしてくる。澄み渡るしじまに、綺羅星が通り過ぎていく。眼を瞑ると、瞼の裏側からも綺羅星がまたたいている。そのまま、佇んでいる。
次の日とも思われるほど、気付けば時間が経っていたかもしれない。すっかり額に同化した掌を窓際に持っていくと、氷片に触れたように、わずかに熱が引いた。うなだれたまま手を下ろすと、淋漓と一滴の水が落ちていった。その場で息を含むと、なにかしら気付かないで、待ち時間に寒気でも入ったのか、清冽とした空気が胸に流れ込んでくる。冷えた空気は喉を驚かせた。少し息が詰まり、大きく吐き出して、顔を上げる。窓からは春が消えたように、薄黒い、器のようなクレーターが拡がっている。濡れたということは、雨漏りさえあるのかと天井に視線を送ったものの何も無く、視線は滑っていった。
窓の外は闇が一様に拡がっていて、見えるものは車内の灯りが依存する程度にしか見えず、すぐ諦めた。頬杖を突いて前の座席に脚を放った。
手元の端末が光って、時刻が並ぶ。胡乱げに手元に持ってきて、盤面を読んだ。それほど時間は経っていなかったらしい。連絡先も入っておらず、ただ時刻を写すだけの端末。ふと画面が消えた。天井から降りてくる電灯と、自分の顔が反射する。切り絵のように浮かび上がって、稜線がいやにはっきりしている。正視すると、そこに吸い込まれてしまうような、何も無い、漆黒の盤面に陥る錯覚が起こって、血の気が引いた。奥行きが無く、無慈悲に写るものだけが渦巻いている。
爪が端末に当たって、かちかちと音を立てている。それが自分の手の震えによるものだと気付くのに、しばらく時間がかかった。掌に力を込めた時、車体は大きく横に揺れた。右に揺れたときに肩が窓にぶつかり、続いて逆側に揺れた。二、三度そうして揺れるうちに揺れ幅は小さくなったが、金属の擦れる音が響いていた。張り詰めていた空気は打ち破られ、叫びに呼応して動揺が膨らみ始めていた。呼吸が浅く速くなっていくのとは裏腹に、窓を過ぎる景色はゆるやかに速度を落としつつあり、呼応して軋む音が大きくなってきている。
車掌が入ってきた。車掌は深々と一礼して、相変わらずのぼそぼそとくぐもった声で、「扉が開きます」とだけ発した。合わせて、反対側の扉が開き、空気が流れ込んでくる。
「ここで止まるんですか?」
「おそらくは。保証はありません、ついに君の……」
車掌はそれだけ早口で答えて、扉の向こうに降りていった。扉に近づいていくと、全身を冷たい波が覆った。耳朶と鼻先を、湿気った風で塗られていく。目は乾き、手は震えている。向こうには、もはやレールは認められない。足を波から上げて、前に出した。一歩、そして扉に手をかけて、震える腕を、逆の手で握りしめた。
稜線が曖昧になった山が、目の前に佇んでいる。白い山だった。足下は砂礫で、歩くたびに足裏に尖った痛みが走る。黒い石は容赦無く待ち構え、そのたびに歯を食いしばらざるを得なかった。駆け抜ける風が、遠吠えを走らせ、あくまでも前身を阻もうとする。決して緩やかでは無い傾斜に、体を前のめりにして、砂礫から足を引き?がし、前に出す。一歩に、砂礫は薄い錫のような音を立てて割れていく。颶風は呼吸を妨げ、大きく肩を広げた。鼓動はすでに自分の耳にも聞こえるほどになっている。汗ばんだ体に憂い、眉間に力を入れた。悔悟しそうになり、頭を振った。膝の歯車が軋み、嘔吐感が込み上げてくる。下腹部が締め付けられ、胸元が熱くなる。一度立ち止まり、呼吸を整えた。振り返れば、遙か向こう、麓は影に隠れて見えなくなっている。バッカスの海の中にある深淵に息を呑んだ。山頂に目を向け、手を握りしめ、また一歩を出した。
堅固に、踏破を意識付けた足は、それでも前に向かっている。気付けば風は弱くなり、むしろ、背中を追いかけるような流れすらあった。前のめりになることも要らないで。陽光が赤く山の稜線を描き始める。足下明るく、山は白く、傷などに怖じ気づくことも無くなり、不死の人かのように。
……空を見る。青く、丸い天体が上にある。あり得ることなら、いつかみんなが、自由を掲げて、そこに届けられる日があるとして。